自発性・双方向性のある学びスタイルをしていきたいと思った話。
- 2025.11.08
- インプット・勉強法

ありがたいことに、外部から「講師をしてください」と依頼を受けることがあります。
よほど条件が異ならない限り、受けるようにしています。
ただ、学びのスタイルとして「自発性」「双方向性」を大事にしています。

*皆さんにAIを動かしてもらいました
「研修」ではなくて「学びの場」
一方的に講師が話す「研修」ではなく、参加した人たちとの双方向性を大事にする「学びの場」のほうがいいな、と思ったきっかけは私が参加した「flier book camp」という講座です。
こちらは本のコミュニティ(flier book labo)が母体ですが、定期的に一定の期間(4ヶ月程度)講座を受けられる「Camp」という制度があります。
これまで、私も3つの講座に参加してきました。

flier book labo|読書コミュニティ
この講座の大きな特徴は、受動的に講師の話を聞くのではなく、「自ら学びを発見する」姿勢が求められるということです。
実際、私が受けた講座はすべて「実践」が求められました。
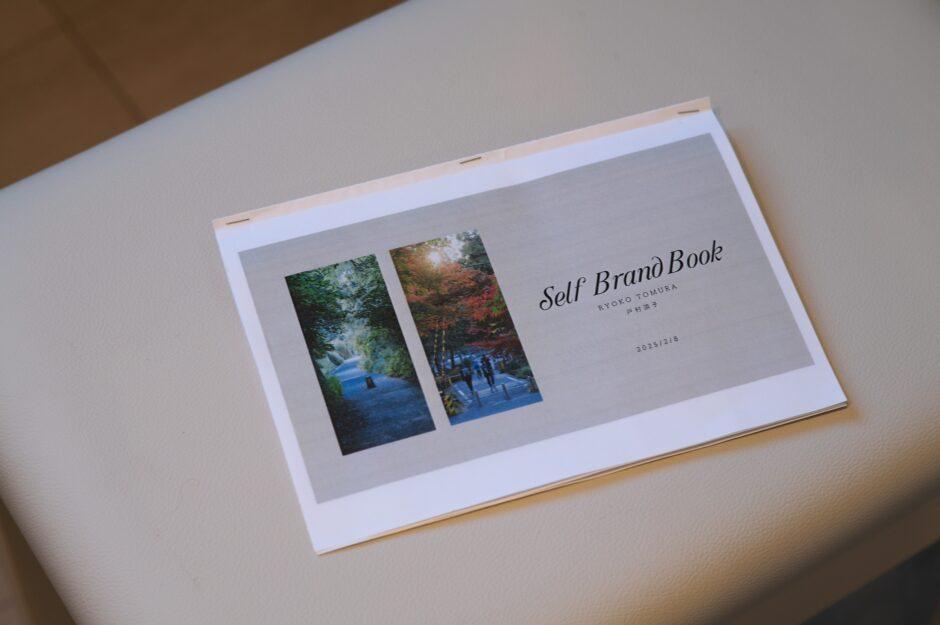
*セルフブランディングブックも作りました
また、同じ講座に参加した人たちとも4ヶ月間、ずっと関わり続けるのも大きな特徴です。講座以外の時間も、時間をとって進捗をシェアしたり、読書会のようなものもやりました。
これが本当によかったんですよね。
学びを自分事として捉え、双方向性の学びをする
というのも、「学びを自分事として考える」ことができるからです。
これは、「研修◯時間義務」といった、外部から強制された学びと大きく異なります。学びたいから学ぶ。それが本当の学びスタイルだと思います。
私は現在、強制された学びは何もしていません。自分が必要と思ったもの、学びたいと思ったものを能動的に学んでいます。独立して仕事している以上、勉強しなかったら自分が大きな損害を被ることになるのは十分わかっています。研修時間◯時間以上の義務とか、筋の悪い学びスタイルだと思います。
学びを自分事として考えるためには、情報をただ受け取るだけでは不十分で、自発性、そして双方向性の学びが大事と感じています。
双方向性のある学びの「場作り」は練習が必要
最近、税理士会(同業者団体)の研修(←言い方は気に入らない)、会計大学院の授業をさせていただきました。
税理士会の研修は、「講義形式」が基本です。でも、私は双方向性のある「ワークショップ形式」を希望しました。恐らく、私以外にこういった形式の研修をしている税理士の方はいないと思います。(テーマが「生成AI」なのでやりやすいというのもありましたが)

会計大学院での授業も、私以外の方(税理士の実務家の方)はすべて講義形式でしたがここも希望してワークショップ形式にしてもらいました。
結果として、とても良かったと思っています。
参加した方にとっては強制的にアウトプットを求められるので大変な面、ただ聞いてるだけではなく手と頭を動かすことで記憶に残る内容になったと思います。
今回、双方向性のある学びの「場作り」は、flier book campさんを参考にしてさせてもらいました。特にオンラインで行った会計大学院の授業では、ブレイクアウトルームを使って生徒同士で議論してもらったり、チャットを使って全員に発言してもらうよう努めました。
私は皆さんの様子を見て、内容をアジャストしたり、補足したり、ということをその場でしました。これはこれで結構頭を使います。むしろ、他の人と同じようにスライドに従って「教える」スタイルのほうが楽でしょう。
でもこういった「ディレクション」「ファシリテーション」こそ、AI時代に求められる人間としての力じゃないか、とも思っています。AIには絶対できないことだから。
情報はAIで出揃ってるし、人より抜きん出て情報を素早くキャッチして「教える」スタイルは古くなっていく。今後は、「みんなで学ぶ」「学ぶ場を作る」スキルがより重要になってくると思っています。
またこういった学びの場、作りたいです。
編集後記
研修&観光のため姫路に二泊。最終日は、またアーモンドトーストを食べにカフェへ。厚切りのトーストが本当に美味しかったです!アーモンドトースト、家で作れないかなあ。


新幹線乗る前に、兵庫県歴史博物館に行きました。「童謡と大正ロマン」というテーマで展示をしていて、わらべうたなど懐かしい歌が紹介されていました。

姫路駅周辺は、道が広くて歩きやすいですね。(鎌倉とつい比べてしまった…)

姫路城は、2年前に行ったので今回はおあずけ。
夕方帰ってきて夜は会計大学院での授業2コマ目。テーマはAIリテラシーでした。
皆さんと学びを共有できて、よかったです。
最近のあたらしいこと
カフェのんのん
兵庫県歴史博物館
おかめ弁当
メニュー
メディア
-
前の記事

日帰り出張はしない。人間のスピードを取り戻す。 2025.11.06
-
次の記事

メモを残すことよりも、メモを取るプロセスが大事なのかも 2025.11.20